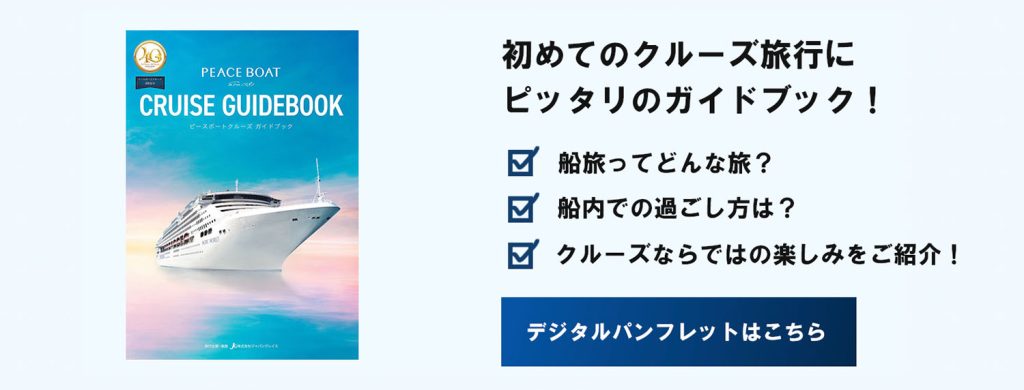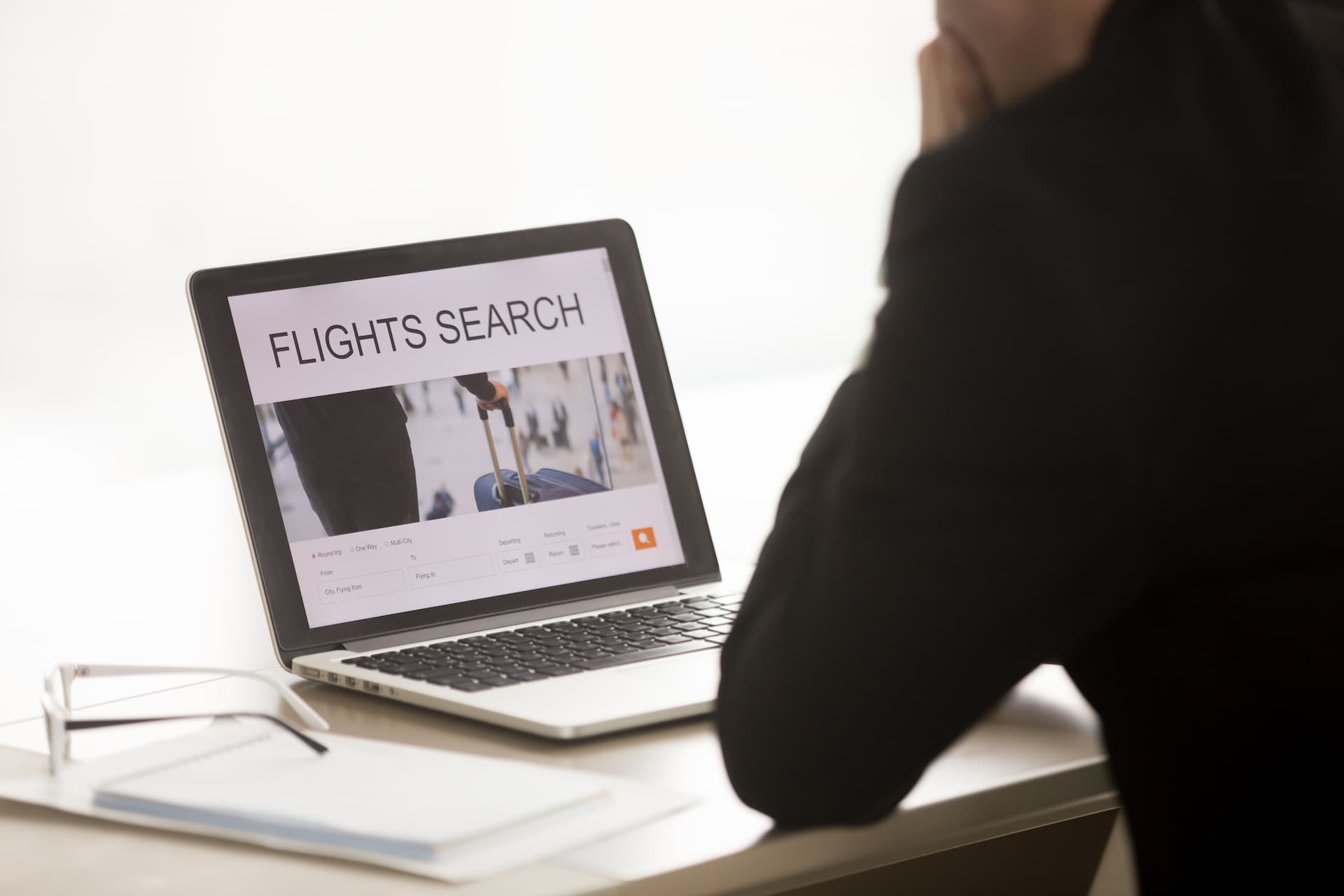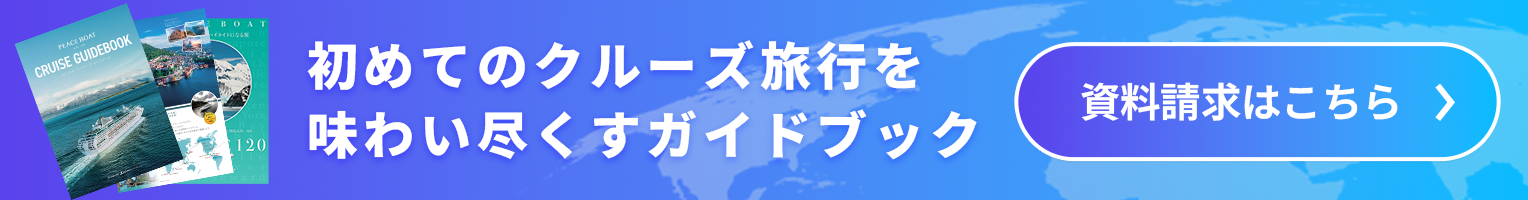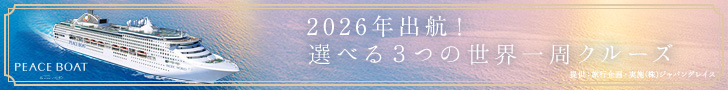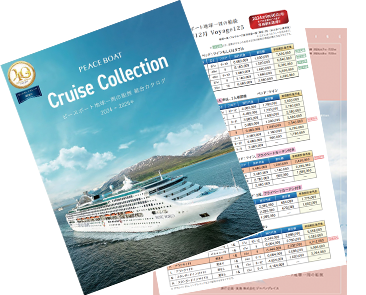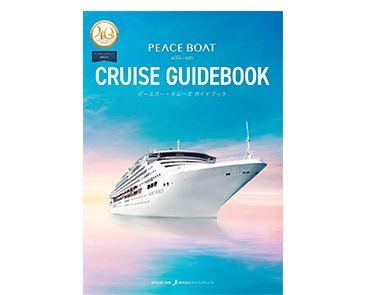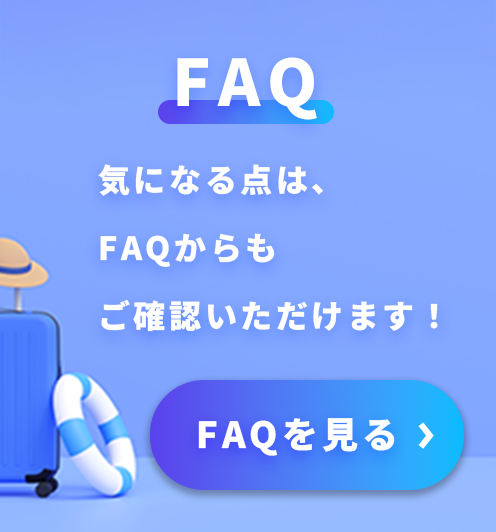03.27

アジアとヨーロッパを結ぶボスポラス海峡とは?クルーズの見どころも紹介
「ボスポラス海峡とはどんなものだろう」「ヨーロッパとアジアを結ぶ歴史の交差点に行ってみたい」そういった考えを持っている人も少なくないはず。
本記事では、ボスポラス海峡の基本情報を紹介します。さらに、クルーズ観光の主要スポットやベストシーズンも解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
アジアとヨーロッパの架け橋ボスポラス海峡とは?
ボスポラス海峡は、トルコのイスタンブールにあり、アジアとヨーロッパの境界線にもなっている海峡です。北にある「黒海」と南の「マルマラ海」を結ぶ水路であり、イスタンブール市内を南北に貫いています。そのため、イスタンブールはアジアとヨーロッパの両方にまたがっている世界で唯一の都市でもあるのです。
古代から現在に至るまで、アジアとヨーロッパ、東西文明の交差点としての役割を果たしており、交易や軍事の重要な地点でもあります。昔から人々の交流が盛んだったため、さまざまな歴史や文化が育まれてきました。ですので、海峡沿いには歴史的な宮殿や要塞、モスクなどが点在し、訪れる人々に多様な景色を見せています。
「ボスポラス」という海峡の名前は、ギリシャ神話に由来し、「牝牛の渡渉*」を意味しています。神話によると、ゼウスは不倫相手のイオを牝牛に変えて隠そうとしたのですが、妻のヘラに見破られ、怒ったヘラがアブ(虻)を放ちました。イオは牛の姿のままで世界中を逃げ回り、この海峡を泳いで渡ったことから、この名前がついたとされています。またトルコ語では”海峡の内”を意味する”ボアジチ (Boğaziçi)”と呼ばれ、”イスタンブール海峡”としても知られています。
*渡渉(としょう):川などを歩いてわたること。かちわたり。
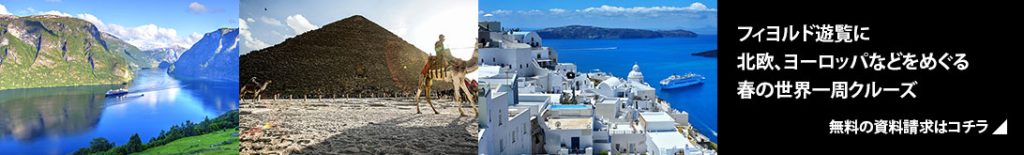
ボスポラス海峡の基本情報
GoogleMap: Bosphorus
※地図画像はイメージです
全長約30km、最狭部は約700mの幅のボスポラス海峡は、国際的な海運にも重要な役割を担っています。ここでは観光に関する基本情報をみていきましょう。
| 所在国 | トルコ |
| 国旗 | |
| 人口 | 8,533万人 (トルコ)/1,566万(イスタンブール)* |
| 言語 | トルコ語(公用語):イスタンブールなどの都市では英語も使用 |
| 通貨 | トルコ・リラ:TRY |
| 為替レート | 100トルコ・リラ:2.73米ドル(2025.3月時点) |
| 物価 | 日本の1/2〜1/3程度:水500ml(約30〜50円) |
| 時差 | UTC+3、JST-6(日本-6時間) |
| 平均気温 | 暖かい時期(6〜9月):最高平均26℃、最低平均19℃ 涼しい時期(11月〜3月):最高平均12℃、最低平均6℃ |
| 観光ベストシーズン | 9~11月(秋は温暖で過ごしやすく、晴れる日が多い) |
*参考:世界銀行2023年
ボスポラス海峡クルーズの見どころ
ボスポラス海峡クルーズはイスタンブールの主な観光の一つであり、海上からさまざまなの景観を堪能できます。クルーズで巡れる主要スポットを紹介します。また、クルーズだけでなく中を見学できる建物もありますのでそちらもおすすめです。
ボスポラス大橋|全長1kmを超える大橋

1973年に完成したボスポラス大橋は、全長1,510メートルで、アジアとヨーロッパを直接結ぶ初の橋として開通しました。ボスポラス海峡をまたぎ、経済・文化の交流を支える役割を担っています。建設当時は世界最長の吊り橋で、トルコの発展を象徴するインフラの一つとして、多くの人々に利用されています。夜には美しいライトアップが施され、幻想的な雰囲気を醸し出します。
ガラタ橋|旧市街と新市街を結ぶ
ガラタ橋は、金角湾(Golden Horn)に架かるイスタンブール旧市街と新市街を結ぶ橋です。1994年に完成した橋で、長さ490メートル、中央部は船の通行のために開閉可能な構造になっています。
この橋は珍しい二層構造になっています。上は車やトラム、人などが通る道で、下はレストランやカフェが並ぶ商業スペースです。釣りを楽しむ市民の姿も名物で、地元の人々や観光客で賑わっています。ほかにも、夕暮れ時には美しい景色をみられるサンセットスポットとしても人気です。
ガラタ塔|新市街のシンボル

イスタンブール新市街のベイオール地区にあるガラタ塔は、14世紀ジェノヴァ人によって建設された石造りの塔です。高さ約67メートルあり、展望台からはイスタンブール市内やボスポラス海峡を一望できます。
オスマン帝国時代には見張り塔として使用され、その後も時代と共に牢獄や火の見櫓*など、さまざまな用途で活用されてきました。現在は展望台として開放され、多くの観光客が訪れる人気スポットとなっています。
*火の見櫓(ひのみやぐら):火事を警戒するため登ったり、火災時に出火場所の方向などを見定めるために登る櫓(やぐら)
ドルマバフチェ宮殿|オスマン帝国時代の壮麗な宮殿

ドルマバフチェ宮殿は、19世紀にオスマン帝国のスルタン・アブデュルメジト1世によって建設された宮殿です。ヨーロッパのバロック様式やロココ様式を取り入れた華やかな建築が特徴です。
宮殿内部は、重さ4.5トンの世界最大級のシャンデリアや金箔で装飾が施された広間があったり、宮殿の床のうち約4,500平方メートルが絨毯で覆われていたりと、その豪華さは圧巻でしょう。
かつてはオスマン帝国の行政の中心地として機能し、最後のスルタンもここで暮らしました。現在は一般公開されており観光できますが、一部は迎賓館としても利用される国が管理する格式ある宮殿です。
ベイレルベイ宮殿|バロック様式とオスマン様式の離宮

ベイレルベイ宮殿は、19世紀にオスマン帝国のスルタン・アブデュルアジズによって建設された離宮で、ボスポラス海峡のアジア側に位置します。バロック様式とオスマン様式が融合した優雅なデザインが特徴で、宮殿内には精巧な木彫装飾やクリスタルシャンデリアが施されています。
かつては迎賓館として使用され諸外国から多くの賓客を迎えました。現在はドルマバフチェ宮殿と同じように一般公開されており、その美しい庭園や豪華な内装を見学できる観光スポットになっています。
ボスポラス海峡の交通インフラと日本企業の貢献
ボスポラス海峡には、ヨーロッパとアジアを結ぶ重要なインフラとして、3つの大きな橋と海底トンネルが整備されています。それぞれの橋の開通年月やおもな仕様について、以下の表にまとめました。
| 名称 | 開通年月 | 全長 | 幅 | 高さ |
| 第1ボスポラス橋 (7月15日殉教者の橋) | 1973年10月 | 1,560m | 33.4m | 64m |
| 第2ボスポラス橋 (ファーティフ・スルタン・メフメット橋) | 1988年7月 | 1,090m | 39m | 64m |
| 第3ボスポラス橋 (ヤウズ・スルタン・セリム橋) | 2016年8月 | 2,164m | 58.5m | 70m |
この中でも第2ボスポラス大橋は、日本のODA(政府開発援助)によって建設されました。この橋は、急増する交通量を支えるために計画され、日本の企業(IHI、三菱重工業、日本鋼管、伊藤忠商事など)が携わり、高い耐久性と安定性を誇る設計が採用されています。完成後は、イスタンブールの交通渋滞を大幅に緩和し、物流の効率化に大きく貢献しています。
また、ボスポラス海峡の海底を通る鉄道トンネル「マルマライ」も日本企業が関わったプロジェクトの一つです。2004年に建設が始まり、2013年に開通しました。全長13.6kmのこのトンネルは、海峡の地下約60mを通過し、ヨーロッパ側のスィルケジ駅とアジア側のウスキュダル駅を結んでいます。
マルマライの開通により、イスタンブール市内の渋滞が緩和され、通勤時間の短縮や物流の効率化が実現しました。このプロジェクトにも日本の技術と資金が活用され、ボスポラス海峡の交通網整備に大きな貢献を果たしています。
ボスポラス海峡を訪れたピースボートクルーズの歴史
ピースボートクルーズは、過去にボスポラス海峡を訪れ、その歴史や文化の体験をしてきました。イスタンブール寄港の際には、ボスポラス海峡の美しい景色や歴史的建造物を巡るプログラムもあります。以下より開催したツアーの詳細をご覧ください。
【2027年】イスタンブールに寄港するクルーズプラン紹介
※本記事にはピースボートクルーズで訪問しない場所も含まれています。詳しくは各クルーズのご案内をご覧ください。
さいごに、イスタンブールに寄港するクルーズプランをご紹介します。
地球一周の船旅 2027年8月 Voyage127
このクルーズではイスタンブール観光のベストシーズンの9月に寄港します。ボスポラス海峡の美しい景色を楽しみながら、アジアとヨーロッパのそれぞれの文化や世界遺産に登録されているイスタンブール歴史地域を巡ることが可能です。
ほかにも、世界遺産の宝庫ポートサイド(エジプト)、大航海時代を象徴する華やかな街・リスボン(ポルトガル)、世界有数の大都市ニューヨーク(アメリカ)、など多くの街にも寄港します。そしてこのクルーズでは海上からオーロラを見られるチャンスがあります。ベルファスト(イギリス)からレイキャビク(アイスランド)へ航行中の5日間です。
ボスポラス海峡やオーロラと共に世界各地の街並みと古代都市が堪能できる世界一周クルーズプランです。